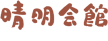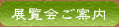令和8年1月6日(火)〜 5月17日(日)「ゆめのうき世に」後期展を開催致しております。
「ゆめのうき世に」展
葛飾北斎、歌川広重の名所絵や喜多川歌麿の美人画、東洲斎写楽の役者絵など、現代の私たちをも魅了し続ける浮世絵は、江戸時代を代表する大衆文化であり、19世紀後半からすでに国際的な人気を誇る日本美術の一つです。当世、つまり当時の「今」のことを題材にしたこのような絵を「浮世絵」と呼ぶようになったのは、天和年間(1681〜84年)頃、《見返り美人図》で知られる菱川師宣の全盛期だといわれています。
「うきよ」という言葉はそれよりずっと昔から使われていましたが、古くは「憂世」という漢字が当てられることが多く、憂うべきつらい世の中、人生といった意味合いでした。中世以降の用例では、仏教的な観念が浸透したためか、無常の世を儚んだり、幽玄の境に身を置くような心持ちが強まってきます。たとえば平氏一族の盛衰を語る『平家物語』に「うきよ」という言葉は何度も出てきており、
言葉と物語がお互いのムードをつくりあげているかのようです。そして近世に入ってくると、つかの間の仮の世だからこそ楽しもうという気分が高まり、人々は「今、ここ」にある現実にフォーカスしていきます。
この心性の変化は、桃山時代以降、都市風俗図や野外遊楽図が盛んに描かれるようになったことと関連しているといえるでしょう。説話や物語を説明するための絵ではなく、同時代を生きる人々の暮らしが主題として選ばれるようになった訳です。次第にそれらの場所に集う人々の姿がズームアップされ、往来を眺める様子から室内へ、さらには遊女や役者個人へと視線は移っていきます。もっという
と、ただありふれた日常というよりは、新奇で艶をまとったものにリアリティを感じ、人々は熱狂しました。そうして江戸時代に生み出されたのが浮世絵なのです。
夢のように儚い世の中で、現を実感すること。逆に現を生きながら夢を抱くこと。繰り返される日々の生活を労働や家事で慌ただしく過ごす私たちが励まされるのはそういう瞬間ではないでしょうか。本展ではそんな気持ちが投影されているような浮世絵や、そのルーツといえる作品、また浮世絵を受け継いでいると考えられる作品の数々を所蔵品の中からセレクトして展示します。
解説 松田愛子